(2023年4月18日更新)
主旨
HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。これまでの2種類に加えて、令和5年4月から新たに9価のHPVワクチンが公費で接種できるようになりました。
HPVワクチン接種についてはこちら
9価ワクチンについて
HPVには多くの種類(型)がありますが、9価ワクチンはそのうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンで、子宮頸がんの原因の80%~90%を占める7種類(※)のHPVの感染を予防することができます。
※16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型
(参考)
2価ワクチンでは、子宮頸がんの約50%~70%を占める16型、18型のHPVの感染を予防することができ、4価ワクチンでは尖圭コンジローマなどの原因となる6型、11型が追加されたワクチンとなっています。
9価ワクチンの接種方法
3回接種又は2回接種(※)
▶2回目は初回接種の2か月後、3回目は6か月後
※15歳までに(15歳未満)1回目の接種を済ませた場合は、5か月以上の間隔をおいて2回接種とすることができます。
2価または4価HPVワクチンとの交互接種について
同じ種類のワクチンでの接種を原則としています。
WHO(世界保健医療機関)では「HPVワクチンは、それぞれ異なった特性を持ち、内容と適応も異なることから、同じワクチンで接種するよう努力がなされるべき」としています。
ただし、前回の接種の種類が不明もしくは入手不可能な場合は、いずれかの種類のワクチンでスケジュールを完了させることも可能としています。
9価ワクチンの副反応について
接種後に次のような副反応が起こることがあります。
接種後に体調の変化や気になる症状が現れた場合は、まずは接種を受けた医療機関にご相談ください。
|
発生頻度
|
報告のあった症状
|
|
50%以上
|
疼痛(痛み)
|
|
10~50%以上
|
腫れ、赤み、頭痛
|
|
1~10%以上
|
浮動性めまい、吐き気、下痢、かゆみ、発熱等
|
|
1%未満
|
嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、
|
|
頻度不明
|
感覚鈍麻、失神、四肢痛
|
リーフレット
小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ
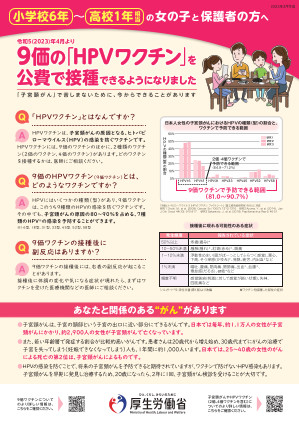
平成9年度生まれ~平成18年度生まれまでの女性へ
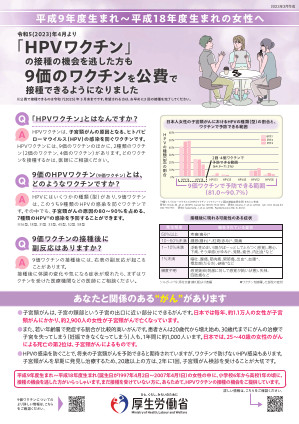
(各画像をクリックすると拡大します)